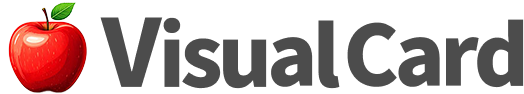世界には約7,000もの言語が存在するとされますが、その多くは話者数が極めて少なく、地域的にも限定されています。それに対して、使用者数が多く、国際的に影響力のある言語はごく一部に集中しています。
この記事では、母語話者および第二言語話者の合計に基づいたデータ(2025年現在 Ethnologue/Britannica 他)を用い、世界で「特に使われている言語」を具体的に解説します。地域別に10のエリアに分類して、各地域で最も重要な言語をまとめました。
世界を10エリアに分けた主要言語マップ
地域別に見ると、歴史的・政治的・経済的要因が言語の影響力を形作っており、旧植民地地域では宗主国の言語(英語・フランス語・ポルトガル語など)が共通語として定着し、教育や行政にも残っています。一方、ヒンディー語や中国語のような国内多数派言語は、人口規模ゆえに国際的重みを帯びています。
1.北アメリカ
英語が圧倒的多数。米国・カナダで共通言語。
1. 英語(アメリカ・カナダ)
2. スペイン語(アメリカのヒスパニック系人口・メキシコ)
3. フランス語(カナダ・ケベック州)
2.中南米(ラテンアメリカ・カリブ海)
1. スペイン語(中南米ほぼ全域)
2. ポルトガル語(ブラジル)
3. 英語・フランス語・オランダ語(一部のカリブ諸島)
3.西ヨーロッパ
英語・フランス語・ドイツ語が多国間で使用。
・英語(イギリス・アイルランド、国際ビジネスでも強い)
・フランス語(フランス・ベルギー・スイス)
・ドイツ語(ドイツ・オーストリア・スイス)
4.東ヨーロッパ・ロシア
ロシア語を中心に、多種のスラブ諸語。英語は若い世代で拡大中
・ロシア語(ロシア・旧ソ連諸国)
・ポーランド語・チェコ語・ウクライナ語など各国語
5.中東
アラビア語(標準形と方言)、イランでペルシア語、トルコではトルコ語。英語はビジネス・教育で広く補助的に使われています。
・アラビア語(地域全域で主要言語)
・ペルシャ語(ファルシ語)(イラン)
・トルコ語(トルコ)
6.北アフリカ
アラビア語と旧宗主国由来のフランス語が併存。
・アラビア語(モロッコ〜エジプトまで広範囲)
・フランス語(旧フランス植民地:モロッコ・アルジェリア・チュニジア)
・英語(徐々に浸透)
7.サブサハラ・アフリカ
英語・フランス語が主要共通語に。スワヒリ語も東アフリカで重要な言語です。
・フランス語(西・中央アフリカで広く使用)
・英語(ナイジェリア・ケニア・南アフリカなど)
・スワヒリ語(東アフリカ広域の共通語)
・多数の地元言語(ヨルバ語・ズールー語など)
8.南アジア(インド・周辺国)
ヒンディー語が最大規模、英語が共通公用語、ウルドゥー語・ベンガル語なども重要。
・ヒンディー語(インドで最大規模)
・英語(インド・パキスタンで公用語的役割)
・ウルドゥー語(パキスタン)
・ベンガル語(バングラデシュ・インド東部)
9.東アジア
中国語(普通話)、日本語、韓国語。英語は教育・ビジネス語として浸透。英語は教育やビジネスで強い。
・中国語(普通話)(中国・台湾・シンガポール)
・日本語(日本)
・韓国語(韓国・北朝鮮)
10.東南アジア・オセアニア
インドネシア語・マレー語、タイ語、ベトナム語、フィリピンのタガログ語。英語も広く通用。
・インドネシア語/マレー語(インドネシア・マレーシア)
・タイ語・ベトナム語・タガログ語(フィリピン語)
・英語(フィリピン・シンガポール・オーストラリア・ニュージーランド)
世界で特に使われている言語
全体的におおまかな傾向をまとめると母語人口で最大の言語、母語人口トップは中国語。国際利用トップは英語。世界で最も広く国際的に使われる言語。また、今後存在感が増す可能性が高い言語、急成長している言語はヒンディー語(人口増加とIT産業の発展)、フランス語(アフリカで若い人口が増えている)です。
以下は、母語話者+第二言語話者の合計数に基づくランキングから、特に使用規模の大きい言語を選んでいます(Ethnologue 2025):(話者人口は概算、母語+第二言語含む)。
英語:約15.28億人(母語約3.90億人+第二言語約11.38億人)
母語は約4億人と意外に少なく感じますが、第2言語として圧倒的にたくさんの国で使用されています。
ゲルマン系言語にノルマン征服以降のフランス語やラテン語が加わり形成。16世紀以降の大航海時代と植民地支配により、世界中に拡散(Crystal, English as a Global Language, Cambridge University Press, 2003)。
科学技術、航空、国際ビジネス、インターネットの主要言語。第二言語話者が母語話者を大きく上回る唯一の言語。国際共通語(リンガフランカ)、ビジネス・科学・IT・外交で必須の言語です。
中国語(標準語):約11.84億人(母語約9.90億人+第二言語約1.94億人)
母語話者世界最多で使用されている言語。中国本土・台湾・シンガポールを中心に使用。古代漢語から発展し、漢字による統一された文字文化を形成。20世紀に中華人民共和国が「普通話(標準語)」を推進し全国的に普及しました(Norman, Chinese, Cambridge University Press, 1988)。
母語話者数が世界最多。経済的・政治的影響力の拡大に伴い、国際的な学習者も増加。
経済的影響力から学習者も増加中。
ヒンディー語:約6.09億人(母語約3.45億人+第二言語約2.64億人)
主にインドと周辺地域で使用されている言語です。インド・アーリア語派に属し、サンスクリット語に起源を持ち、デーヴァナーガリー文字で表記。1947年のインド独立後、英語と並び連邦公用語に指定(Masica, The Indo-Aryan Languages, Cambridge University Press, 1991)。
インド国内で最大の話者人口を持ち、映画(ボリウッド)やメディアを通じ文化的影響力も大きい。インドでは英語と並び公用語になっています。
スペイン語:約5.58億人(母語約4.84億人+第二言語約0.74億人)
ラテンアメリカ全域とスペイン。ラテン語から派生したロマンス語の一つ。15世紀以降、スペイン帝国の拡張に伴いラテンアメリカ全域に広がる(Penny, A History of the Spanish Language, Cambridge University Press, 2002)。
21カ国で公用語。米国でも使用人口が急増しており、国際機関でも公用語としても存在感が大きく、重要な地位を占めています。
フランス語:約3.12億人(母語約0.74億人+第二言語約2.38億人)
フランスだけでなく、アフリカで広く使用されています。ラテン語から派生。中世以降ヨーロッパの外交言語として支配的地位を確立。19〜20世紀の植民地拡張でアフリカやカナダに広がる(Walter, French Inside Out, Routledge, 2003)。
国連・EU・オリンピック委員会など国際組織で公用語として重要な言語になっています。アフリカで使用人口が増加しており、将来的成長が注目されています。
標準アラビア語:約3.35億人(主に第二言語として)
中東・北アフリカを中心に多数の国で公用語。古典アラビア語は『クルアーン』の言語であり、7世紀以降のイスラム拡張とともに北アフリカから西アジアに広がった(Versteegh, The Arabic Language, Edinburgh University Press, 2014)。
イスラム教徒にとって宗教的に神聖な言語。コーランの言語として宗教的に強い意味を持っています。国連公用語のひとつ。方言差が大きく、書き言葉(フスハー)と話し言葉に乖離があります。
ポルトガル語(約2.6億人)
ブラジルを中心に使用。南米で大きな存在感があります。ラテン語から派生。15〜16世紀の大航海時代にアフリカ、南米、アジアに広がった。特にブラジルで定着(Teyssier, História da Língua Portuguesa, 2004)。
ブラジルの経済的規模により世界的影響が大きい。8カ国で公用語になっています(CPLP:ポルトガル語諸国共同体)。
ロシア語(約2.5億人)
ロシアおよび旧ソ連圏で使用されています。スラブ語派の一つ。キリル文字で表記。ソ連時代に旧ソ連圏全域に拡大しました(Comrie et al., The Russian Language in the Twentieth Century, Oxford University Press, 1996)。
国際宇宙ステーションの公用語。東欧・中央アジアで依然として共通語として利用されています。政治・軍事的影響を背景に地域的共通語の役割を保持しています。
まとめ
世界における言語の分布を見ると、使用規模が極端に大きい言語がごく少数に偏っている現実が浮かび上がります。英語は、母語での使用人口は約3.9億人ですが、第二言語使用者は約11.4億人にのぼり、国際共通語として圧倒的な影響力を示しています。
一方、中国語は母語として最多ですが、第二言語話者は比較的少なく、地域的影響力は限定的であることが分かります。
ヒンディー語、スペイン語、アラビア語、フランス語もそれぞれ地域や文化圏で強い存在感を持ちますが、それらの多くは第二言語話者を抱える点で、英語には及びません。
地域別に見ると、歴史的・政治的・経済的要因が言語の影響力を形作っており、旧植民地地域では宗主国の言語(英語・フランス語・ポルトガル語など)が共通語として定着し、教育や行政にも残っています。一方、ヒンディー語や中国語のような国内多数派言語は、人口規模ゆえに国際的重みを帯びています。
※Ethnologue 2025、Britannica、UN公式言語データなどに基づいています。